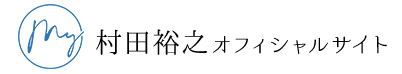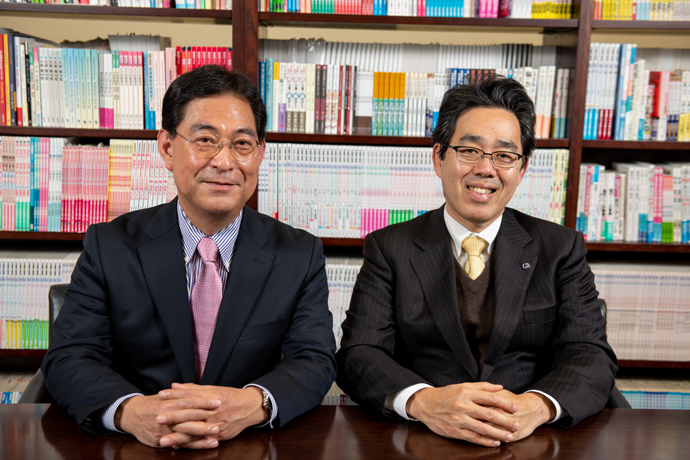シルバー産業新聞 連載「半歩先の団塊・シニアビジネス」第143回
スタバの新業態、日本上陸
2月28日、東京・目黒にスタバの新業態「スターバックス・リザーブ・ロースタリー」が上陸する。この新業態は2014年シアトルで誕生した。その後ニューヨーク、ミラノ、上海ときて、5店舗目が東京だ。
これまで何度か取り上げた通り、スタバは事業の初期段階は豆の販売から始め、次に立ち飲み店に進出。その後、自宅(第一の場所)でも職場(第二の場所)でもない「第三の場所」を提供するというコンセプトを取り入れ現在のスタイルを確立した。
コーヒー以外の価値も提供してきた。たとえば、店内の無線LANはスターバックスが先駆的に始めたサービスだ。これらの結果、ドーナツやサンドイッチなどかなり割高にもかかわらず、ここだと利用者はつい買ってしまう。
つまり、その場の体験価値を上げれば、価格が多少割高でも、顧客は受け入れる。
「上流工程」という体験価値を提供
このようにスタバは、顧客にとっての「体験価値」を基軸にする「体験経済」(エクスペリエンス・エコノミー)の最大の実践者だ。今回の新業態も実はこの体験経済の延長である。新しい点は顧客に珈琲を提供する前の焙煎などの「上流工程」の体験を提供したことだ。
目の前に珈琲の焙煎機がある作業所が見え、天井を見上げると焙煎された豆が透明パイプの中を次々に運ばれ、そのできたての豆をお洒落な服装のスタッフが顧客の目の前で一杯ずつ薫り高いコーヒーに仕上げてくれる。コーヒーショップというよりは、まるで遊園地のようだ。
先駆者は米国東部のスーパー

しかし、私が知る限り、こうしたコンセプトは実はスタバのオリジナルではない。ニューヨークやコネティカット州にあるスーパーマーケット、ステュー・レオナード(Stew Leonard’s)がその先駆者だ。
この店は、もともと牧場から始まったため、自社保有の農場から牛乳やバター、牛肉を直販する。店の中に牛乳をパックするミニ工場があり、ガラス越しに見ることができる。
こうした製品の「ライブショー」は、店のあちこちで見られる。さらに店内ではパンやマフィン、ベーグルなどをその場で焼いて販売する。
次に、工夫された商品の配列。最初に果物、ベーカリー、野菜、肉、飲み物、魚、チーズやハム、乳製品、最後に鶏肉料理や中華料理の量り売りがあって、レジにたどり着く。普通のスーパーのように四角い配列ではなく、まるで迷路のようにくねくねと回っていく。
また、家族連れが多いためか、子供が楽しめるように、動くキャラクターが店内の至るところに見られる。
食料品販売を中心とするスーパーは、基本的には「生活に必要だから行くところ」である。だが、ステュー・レオナードは、「行くと買う気をそそられるところ」だ。
色鮮やかな商品を立体的なディスプレイやキャラクターで見せる手法は、単なるスーパーというよりエンターテインメント・パークと言えよう。
体験価値が高いと販売効率も上がる
ステュー・レオナードの店舗数は、全米でわずか4店舗だが、1平方フィート当たりの売上高は、3,470ドルで、全米平均500ドルの約7倍。世界一の面積効率でギネスブックにも掲載されている。
一方、取り扱い品目は、通常のショッピングモールが3万品目なのに対して2,000品目とかなり少ない。しかし、顧客から品揃えが悪いというクレームが上がったことはほとんどないという。
顧客にとっては不要な商品を数多く並べられるより、質の高い商品に絞り、心地よい購買体験を演出されるほうが、はるかに体験価値が高い。ステュー・レオナードは、このことを実証している。
スマホ社会ではリアルな臨場体験が価値になる
ということで、スタバの新業態は、このステュー・レオナードをかなり研究していると思われる。重要なことは、なぜ、いまスタバがこのような業態開発を行ったのかだ。
私はその背景にスマホ社会の進展があると思う。
現代社会では、手のひらサイズのスマホで大抵のことができるようになった。しかし、そうした社会になればなるほど、消費者は体全体・五感で感じる体験を強く求めるようになると思う。
映画「ボヘミアン・ラプソディ」が、なぜ、世界中で空前の大ヒットになったのか。観た人は分かるが、あれは単なる映画ではない。10万人以上が参加した34年前の伝説的音楽ライブの臨場体験なのだ。