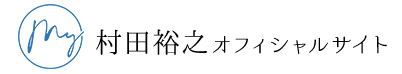週刊エコノミスト臨時増刊10月14日号「65歳雇用」の真実
本日9月30日発売の週刊エコノミスト臨時増刊10月14日号「65歳雇用の真実」に「加速するシニアシフト、ビジネス全開」と題した小論を寄稿しました。
「人生90年」中堅サラリーマンを直撃!とサブタイトルにあるように、この増刊の主題は、人口動態のシニアシフトに伴う労働問題です。多くの労働経済学者、エコノミストの方が寄稿されているなかで、「65歳雇用」制度の新たな側面であるシニア市場拡大の論点を提供するのが拙稿の位置づけのようです。以下に拙稿全文を掲載します。
加速する「シニアシフト」、ビジネス全開 団塊世代が「65歳定年」突入、市場拡大
いま、「シニアシフト」の流れが、あらゆる産業に加速度的に広がりつつある。シニアシフトには2種類ある。1つは「人口動態のシニアシフト」で、人口の年齢構成が若者中心から高齢者中心へシフトすることだ。
1950年の日本の人口構成は、年齢層が若いほど人口が多い「発展途上型」の形をしていた。所得の低い経済発展途上段階では、このような人口構成がよく見られる。これに対して2013年の日本の人口構成は、人口の山が60~65歳の高齢者層に移動し、年齢が若いほど人数が少ない年齢構成となっている。全体として生産年齢人口(16~64歳までの人口)よりも、65歳以上の高齢者人口が増加する傾向にある。
日本の人口動態は、時間の経過とともに、当初若年層が人口の中心だったのが、徐々に高齢者層中心にシフトしてきたのである。このようなシフトは、日本以外の多くの経済先進国でも見られる。
一方、もう1つのシニアシフトは、「企業活動のシニアシフト」。これは企業がターゲット顧客の年齢構成を若者中心から高齢者中心へシフトすることだ。ターゲット顧客を高齢者中心にシフトするには、市場調査、商品開発、商品販売、営業、マーケティング、店舗運営などの事業戦略を大きく変更し、戦略遂行のための組織体制も大きく変更する必要がある。
2012年以降に目立つのは、実はこの「企業活動のシニアシフト」だ。私が知る限り、いま、この「企業活動のシニアシフト」が最も先鋭化している国は、日本である。これは裏を返せば、これまで「人口動態のシニアシフト」が、時間の経過とともに粛々と進行していたにもかかわらず、「企業活動のシニアシフト」は、一部の企業と業種を除いて取り組みが遅れ気味だったからだ。それが、ようやく本気モードになってきたのだ。
なぜ、いま、さまざまな産業で「企業活動のシニアシフト」が起きているのか。実は、2012年は、団塊世代の最年長者である1947年生まれが65歳、つまり定年に達した年なのだ。以降毎年、人数の多い団塊世代が順番に定年を迎え、今度こそ大量の離職者を対象とした新たな事業機会が生まれるとの期待感から一種のブームになっている。このことが理由の1つであるのは確かだ。
しかし、これだけがいま起こっている産業界全体のシニアシフトの大きな流れの理由ではない。実は、6年前の2007年にも「2007年問題」と呼ばれ、似たようなブームが起きた。ところが、今回の動きは6年前の一過性のブームとは大きく様相が異なっている。それは、企業におけるシニアビジネスへの取り組みが本気になってきたこと、取り組む企業の業界が多岐にわたっていることだ。
消費に敏感、先行した小売業界
シニアシフトへの対応をいち早く実行している業界の一つは、コンビニ業界だ。従来、コンビニは「近くて便利だが値段が高い」というイメージが強く、主な顧客層は長い間若い男性で、シニアや女性は少数派だった。ところが、ここ数年シニアや女性の来店者の割合が増えている。国内コンビニ最大手セブン‐イレブン・ジャパンの来店客(1日1店舗当たり平均客数)の年齢別構成比の年次変化を見るとそれがよくわかる(図表1)。
1989年度には30歳未満が63%、50歳以上が9%だったのが、2011年度には30歳未満が33%、50歳以上が30%となっている。30歳未満の割合がほぼ半分になったのと対照的に、50歳以上の割合が3倍以上に増えている。こうした「企業活動のシニアシフト」にいち早く取り組んだ結果、セブン‐イレブンも、ローソンも近年は毎年最高益を更新し続けている。
また、大手スーパーにおけるシニアシフトの動きも活発だ。イトーヨーカドー、イオンやダイエーなど大手スーパーは、従来品揃えの豊富さを売りにするために売り場の広い大型店舗で事業展開してきた。品揃えの豊富さと規模の経済を追求するために、店舗規模を徐々に大型化し、土地コストを下げるために徐々に郊外のロードサイドに出店するようになった。
ところが、こうした郊外の大規模店舗は、シニアにとっては行きづらい場所になる。高齢になるにつれてクルマの運転をしなくなり、足腰の衰えに伴って自宅からの行動範囲が狭くなるからだ。
また、店舗が広いと欲しい商品を探すのにいちいち長い距離を歩く必要があり、疲れる。すると、店舗の広い大型スーパーに買い物に行くのがおっくうになる。高齢化の進展とともに大型スーパーからシニア客が徐々に遠ざかっていったのだ。
こうした状況に陥った反省を踏まえ、スーパー各社では2011年あたりからようやくシニアシフトに本腰を入れるようになった。シニア客に好まれる売り場、商品、サービス開発などにおいてさまざまな取り組みがなされるようになった。
これらの取り組みの結果、店舗では車椅子でも十分通れる広い通路、歩行に難のある人でも乗りやすくした速度の遅いエスカレーターの導入、途中で休憩できる椅子の設置が進んだ。また、文字が大きく見やすい価格表示、欲しい商品が探しやすく、取りやすい棚の導入なども進んだ。
紙おむつ、カラオケ、スマホと続々
一方、コンビニやスーパーなどの小売業以外でも「企業活動のシニアシフト」の動きが目立っている。皆さんは「紙おむつは赤ちゃん用」だと思っていないだろうか?赤ちゃん用の紙おむつ市場は、2011年でほぼ1400億円。ところが、2012年中に大人用の紙おむつ市場が1500億円に達し、ついに赤ちゃん用を逆転した。
日本での紙おむつの生産は、女性の社会進出の増加に伴い1985年以降、年率30%もの急成長を遂げた。しかしその後は、布おむつからの転換が落ち着いたことに加え、少子化の影響で成長は鈍化し、1995年からは減少基調となった。
一方、大人用はここ数年、市場全体が年率5%程度で成長を続けている。国内紙おむつ最大手のユニ・チャームでは、大人用の売上げは2ケタ増が続いており、2013年3月期には大人用紙おむつも売上げ600億円台を突破した。
また、「リカちゃん人形」といえば、子供向けの着せ替え人形の代名詞としてご存じの方も多いだろう。1967年(昭和42年)の発売以降、累計出荷数が5000万体を超えるロングセラー商品だ。
2012年4月、このリカちゃんファミリーに「おばあちゃん」が登場した。年齢は56歳。この歳に設定したのは、リカちゃんを発売した1967年当時、メインターゲットだった11歳の女の子が2012年に56歳になったためだ。
共働き世帯の増加で母方の祖母が孫の世話をするケースが増えており、発売元のタカラトミーには、リカちゃんシリーズの購入者から「孫と遊ぶ時に自分(つまり、おばあちゃん)役の人形があるといい」などとの声が寄せられていたという。
カラオケ店も、もはや若者の場所ではなくなっている。それどころか、平日昼間はむしろシニアが主要顧客になりつつある。業界最大手のコシダカでは、平日昼間は来店客の多くが60歳以上のシニアで、店舗によってはシニア客の割合が6割を超えるところもあるという。
スマートフォン(スマホ、多機能携帯電話)も若者向け商品のイメージが強い。ところが、市場の主戦場はシニア向けに移りつつある。2012年8月に富士通からシニア向けスマホ、「らくらくスマートフォン」が発売された。これは、シニア向け携帯電話として累計出荷台数が2200万台を超えるロングセラーとなった「らくらくホン」の使いやすさをスマホに応用しようとしたものだ。
インターフェイスは字が大きくて見やすいシンプルなメニュー構成、ボタンのように押した感触があって、押し間違えにくいタッチパネルなどにその工夫が見られる。
また、「らくらくパケ・ホーダイ」という専用の料金体系が用意され、らくらくスマートフォンの購入者のみ月額定額料2980円で利用できる。通常の定額サービスだと月額5460円なので、2480円も安くなっている。年金暮らしで財布の紐の固めのシニアに対しても導入の敷居を下げている。
このドコモの動きに追従して、ソフトバンクは今年5月に「シンプルスマホ」を、KDDIも「アルバーノ・プログレッソ」を発売した。ドコモも今年8月に「らくらくスマホ」の改良版である「らくらくスマホ2」を発売し、さらなる差別化を図ろうとしている。
とはいえ、各産業界におけるこうしたシニアシフトの取り組みはようやく本格的に始まったばかりで、まだまだ改善の余地が多いのが実情だ。しかし、こうした取り組みが今後ますます増え、競合他社との切磋琢磨を通じて商品・サービスの質が上がれば、シニア消費者にとっての利便性はどんどん高くなっていくだろう。
シニア消費が日本を救う
実は、こうした「企業活動のシニアシフト」は、単に企業や消費者であるシニアがメリットを享受するだけにとどまらない。経済の活性化と国家財政の改善にも寄与するのだ。
2012年8月10日に消費税増税を柱とする社会保障・税一体改革関連法が参院本会議で採決され、民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決、成立した。現行5%の消費税率は2014年4月に8%、2015年10月には10%へ2段階で引き上げられることになった。2015年10月に、現状に比べて消費税は5%のアップとなる。
ちなみに、この5%分は金額にすると年間13兆5000億円。このうち、約4%の10兆8000億円を社会保障費に回すことになっている。ところが、この分だけ毎年度の国債発行は減らせるが、新たに年金や医療介護費に回せる分はない。残る約1%分の2兆7000億円は、子育て支援などの社会保障の充実に回すことになっている。
しかし、2012年度の一般会計90兆3339億円のうち、社会保障費は26兆3901億円にものぼる。消費税を10%まで増税しても、焼け石に水なのが実態だ。しかも、増税により、生活が一段と厳しくなるという心理面でのマイナス効果で、一段と財布の紐が固くなり、消費が落ち込む可能性もある。つまり、税率をアップして増収を見込んだのに、消費が減って見込んだとおりの税収すら得られなくなる恐れもあるのだ。
シニア資産の3割消費で、国家予算1・6倍分に相当
一方②は、企業活動のシニアシフトである程度貢献可能と思われる。総務省統計局による「家計調査報告」平成22年(2010年)によれば、1世帯当たり正味金融資産(貯蓄から負債を引いたもの)の平均値は、60代で2093万円、70歳以上で2145万円(図表2)。
一方、厚生労働省「国民生活基礎調査」平成22年(2010年)によれば、世帯数は60代で1083・6万世帯、70歳以上で1191・1万世帯である。これらより、60歳以上の人の正味金融資産の合計は、482兆2884億円となる。
このうち、仮に正味金融資産合計の3割、144兆6865億円が消費支出に回ったとすると、消費税率を5%に据え置いた場合、税収は7兆2343億円となる。この数値は、消費税を現状より5%アップした場合の見込み税収アップ分13兆5000億円に対して6・3兆円ほど足りない。だが、シニアの資産が消費に回ることで、消費税をアップしなくても、これだけの税収が見込めることに注目してほしい。
すでに、消費税増税は国会で可決しているので、この話は空論に聞こえるかもしれない。だが、ここで言いたいのは、若年層に比べたシニアの消費支出によるインパクトの大きさだ。前掲の試算は消費税収に焦点を当てているが、実は、増えるのは消費税収だけではない。それ以上に、一般会計90兆3339億円の1.6倍にもなる144兆6865億円という金額が実体経済に回ることが重要なのだ。
ちなみに、先に挙げた正味金融資産(2010年)の平均値は、50代では1109万円、40代では142万円とシニア層に比べて金額が小さい。30代ではマイナス226万円(つまり、貯蓄より負債のほうが大きい)、30歳未満ではマイナス48万円となる。シニア層に比べると若年層の正味金融資産はかなり少ない。若年層の資産の消費はあてにできない。
ただし、シニア層が正味金融資産を多く持っているからといって、それがすべて消費に結びつくわけではない。先行き不透明感がますます強まるなかで、60歳以上の人すべてに正味金融資産の3割どころか、2割を消費に回してもらうことすら現実的でないという意見もあろう。
だからこそ、ここに「企業活動のシニアシフト」の大きな意義がある。商品の売り手である企業が積極的にシニアシフトに注力することによって、買い手であるシニアは、より価値の高い商品や利便性の高いサービスを得られるようになる。
つまり、シニアが必要としていたが、これまで市場にはなかった、より付加価値の高い商品・サービスが多く登場するようになる。すると、「そう、こういう商品が欲しかったのよ」という機会が増え、結果としてシニアの消費も増えると予想される。
シニアの消費が増えれば、先に挙げた消費税収は増える。また、企業の売上げ・収益が増え、業績が向上すれば、法人税などの税収も増える。この結果、国の税収が増え、財政改善に寄与することになる。財政が改善されれば、ギリシャのように財政破綻することもなく、国際的信用を維持でき、シニアも安心して老後を過ごせるようになるのだ。
参考文献:シニアシフトの衝撃