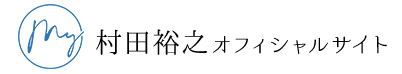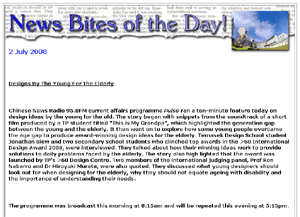2008年5月号 FPジャーナル特集
第1部―1 長寿社会の未来と現実:2030年には「シニア」と名のつくものはなくなる
シニアという言葉には本来年齢の定義はない。だが、筆者が1999年の敬老の日の朝日新聞への寄稿で「まだ介護が不要で元気な50歳以上の年長者」をアクティブシニアと定義したことから、これが日本で広まったようだ。
ところが、特集のタイトルに反して、2030年には「シニアライフプランニング」という言葉はなくなっているだろう。なぜか。
2030年には団塊世代は80歳を超え、人口のうちの50歳以上の割合が54%となる(図表1)。つまり、人口の過半数を50歳以上の人が占めるなかで、敢えて「シニア向け」という必要がなくなるからだ。
かつてモーターが世の中に登場したときに、新技術として脚光を浴びた時期がある。だが、さまざまな商品の一部品として普及するにつれてモーターの差別性は忘れ去られた。これと同様に、全人口に対するシニアの割合が過半数になれば、「シニア向け」という名称に差別性はなくなっていく。
さらに、特に米国で顕著なように「シニア」や「エルダー」といった特定の年齢層を意識した言葉は、年齢差別主義(エイジズム)であるとして、なるべく使用されない方向に時代は向いている。
50歳以上の会員を3,900万人有する団体AARPでは「senior」という言葉は使わず、「older adults」という言葉を良く使う。older adultsとは、日本語に訳せば「年長者」といった意味だ。
このAARPは、米国での「雇用における年齢差別禁止法」の制定に大きな指導力を発揮したのに加えて、米国の年齢差別的な動きを解消する活動を継続的に実施しており、社会的影響力はきわめて強い。
こうした背景も踏まえると、2030年には「シニア」と名のつくものは、ほとんどなくなっていくと予想される。「シニアビジネス」という私の著書も、昔の一時代を記した古典(?)として語り継がれることだろう。
医療技術の革新が新たな商品・サービスを生み出す
一方、シニアライフプランニングという言葉はなくなったとしても、80歳代の団塊世代を含めた年長者向けのビジネス自体はなくならない。それどころか、現在では想像のつかないような新しいビジネスが数多く生まれているだろう。
歴史的に世の中が大きく変化するとき、技術革新がきっかけとなっていることが多い。これからの20年で特に注目されるのは医療技術の革新だ。これにより、人間の寿命が飛躍的に延びる可能性がある。
現在、米国を中心に世界各地で老化のメカニズムを解明する研究が取り組まれている。これらの研究によると、人間の老化には、①神経内分泌説、②フリーラジカル説、③細胞消耗説、④カロリー過剰説、⑤遺伝子支配説の五つがある。
①の神経内分泌説は、体の中に分泌される種々のホルモンが複雑に絡み合った結果、老化するというもの。したがって、こうしたホルモンの分泌を抑制したり、補充したりすることで部分的に老化を防ぐことができると考えられている。
一方、②のフリーラジカル説とは、本来一対で持つべき電子を1つ失っているために過剰反応を起こす電子、フリーラジカルがDNAの突然変異を起こしたり、細胞膜を破壊したりすることで老化するという考え方である。さらに、③の細胞消耗説は、人間の体は使えば使うほど磨り減っていくという考え方、④のカロリー過剰説は、過剰なカロリー摂取が老化の原因だとする考え方だ。
以上の各説に基づき、現在さまざまな商品開発がなされており、すでにいくつか商品化されているものもある。DEHAやメラトニンといったホルモン増強剤、フリーラジカルからの攻撃に対して効果的なビタミンやマンガン、亜鉛といったミネラルを含むサプリメント、細胞の摩耗を緩和するたんぱく質のコラーゲンを補給するサプリメントや化粧品などがその一例だ。今後20年間にこの分野で、さらに多くの商品・サービスが出現するだろう。
団塊世代が80歳代になる頃、寿命150年時代を迎える
興味深いのは⑤の遺伝子支配説だ。これは、老化するのは生まれた時点でプログラムされている遺伝子によって支配されているため、という考え方だ。これによると、人間の寿命は最大限124歳といわれる。人間の場合、細胞分裂の回数が62回までと限定されており、人間の細胞分裂は2年で一巡するので、寿命の上限が124歳となるという。
拙訳「いくつになっても脳は若返る」(ダイヤモンド社)でも紹介した世界最高齢の公式記録をもつフランス人女性ジャンヌ・ルイーズ・カルマン(写真1)は、122歳と164日生きたが、この記録は遺伝子支配説にも一致する。よって、遺伝子情報を徹底的に解明することで、老化を支配しているプロセスを制御できる可能性がある。
こうした遺伝子工学の発展に並行して、近年注目を集めているのは「トランス・ヒューマニズム」と呼ばれる考え方だ。これは「老化現象は病気の一種に過ぎず、その治療や予防は技術革新により可能で、人類は150歳あるいはそれ以上の命をもつことができる」というもの。
こうした考え方をもつ人たち「トランス・ヒューマニスト」によると、今後20年間でこの分野の研究開発が本格的になり、実用化に向かうという。ということは、団塊世代が80歳代になる頃は、寿命150年時代を迎えている可能性がある。
現在の高齢者の定義は65歳以上となっている。ところが、40年以上前には高齢者の定義は55歳以上だった。つまり、こうした定義は平均寿命の関数であり、平均寿命の延びと共に変わっていく。
したがって、平均寿命が150歳になった場合、65歳の人をもはや高齢者とは呼ばないだろうし、80歳の人ですら高齢者とは呼ばないだろう。冒頭にシニアが人口の大多数になるのでシニアという言葉がなくなると述べた。この理由はここに述べたように、寿命150年時代が現実化することでシニアという言葉の意味が大きく変わることからもお分かりいただけるだろう。
寿命150年時代に何が変わるか
さて、人間の寿命が150年になると何が起きるか。寿命が延びるということは人生において何かをやることのできる猶予時間が増えることを意味する。これは人間の潜在能力をさらに開花させる可能性を広げることになる。
しかし、同時に長く生きるための費用も必要となる。たとえば、90歳で寝たきりになったまま150歳まで生き延びれば医療・介護費用が膨大にかかる。だから、寿命が延びる場合は「健康寿命」が延びるのでなければ有益とはいえない。
一方、仮に、ほとんど病気もせず、健康で過ごせるとしても、毎日の生活を維持するための食費などの生活費は必要となる。
さらに、たとえ65歳で仕事を辞めても生活に困らないだけの経済的な余裕があり、健康で過ごせるとしても、65歳以降何もせずに85年間過ごすのは大変な苦痛だ。
つまり、寿命が延びると、その分だけ「お金」と「生きがい」が必要になる。寿命150年時代にはこれらをどうサポートするかが、これまで以上に求められていく。
寿命が延びるとライフステージの質や順序が変わる
FPによる現状のライフプランニングは、日本人の標準的なライフステージを、平均寿命おおむね80歳、離職60から65歳、就職22歳前後と仮定してなされている。
しかし、寿命150年時代となれば、現状のライフステージは大幅に変わらざるを得ない。たとえば、現在のように65歳前後で離職し、悠々自適で暮らすというのは、前述のとおり生活費用の面でほとんど不可能になる。
したがって、たとえば、90歳までは“現役”として収入を得て働き、その後を年金と貯蓄と副収入とで生活するというパターンが一般的になるかもしれない。
年金については、現在のところ支給開始年齢が段階的に上がり、2013年度から65歳からの支給開始ということになっている。しかし、2013年以後も現状のような少子化が続き、前述のとおり“シニア”の割合が増えれば、現在の賦課方式の年金制度は、ますますバランスが崩れ、支給開始年齢をさらに高め、支給額を減らし、保険料を増額しなければ成り立たなくなる。
人間の寿命延長は、この危うい年金制度のバランスをさらに崩す“加速器”の役割を担う。もし、年金制度が存続するとしても、平均寿命が150歳になるのなら、支給開始年齢は、たとえば90歳あるいはそれ以上にならざるを得なくなる。
ライフステージの質が変わると労働市場も変わる
こうしたライフステージの変化は、生涯収入カーブの設計も変えていく。現在の一般的な収入カーブでは、22歳前後で就職してから給与収入が発生し、65歳の退職までおおむね金額も増えていった。退職後に給与収入はなくなるが、退職と同時に支給が開始される年金とそれまで蓄積した資産の利回りや株の配当などが収入となった。
しかし、寿命150年時代には、年金の支給年齢も遅くなり、支給額も少なくなると見込まれるため、年金をあてにしない収入カーブを設計せざるを得なくなる。つまり、誰もが文字通り「生涯現役」に近づいていく。
これらの変化により、年金受給のある年長者と年金受給がない若年者(実はどの程度の年齢を若年者というのかもあいまいになる)との総収入の差が少なくなる。この結果、年齢に関係なく、その人の業績・能力で評価される賃金体系が市場に広く形成されていくことが予想される。
これに併せて定年制度は完全に廃止され、それを後押しする日本版の「雇用における年齢差別禁止法」も制定されるだろう。こうして25歳の人も85歳の人も能力が同じであれば、同じ条件で雇われるようになり、労働市場に大きな変化が起こるだろう。ただし、能力が同じならば、という前提がつく。
第1部―2 長寿社会の歩き方-高齢者の活躍の場とFPの役割
“高齢雇用”増大による課題は何か
第1部-1で述べたとおり、長寿社会とは誰もが「生涯現役」に近づいていく社会である。ということは企業においても高齢者(実は将来において、どの年齢以上の人を高齢者と呼ぶのか、そもそも高齢者という言葉が存在し続けるかわからないが)を雇用し続ける割合が高まっていく。
すでに、その兆候は現れており、65歳以上の人でも正社員として雇用し続ける企業が少しずつ増えている。イオンが定年退職を65歳まで延長したほか、いなげやも現在より3歳上げて68歳にした。また、食品スーパー最大手のライフコーポレーションは本年5月からパート社員の定年を64歳から70歳に引き上げる。
厚生労働省は希望する従業員全員を70歳まで継続して雇用する企業を、雇用保険を活用して1社当たり40万円から200万円程度の財政支援をする予定だ。
ところが、こうした“高齢雇用者”の増大には課題も多い。最大の課題は働く人の「モチベーションの低下をどう防ぐか」だ。高齢雇用者は、会社に勤務し続けてはいるものの、給料は一般に最盛期よりもかなり少なくなる。さらに権限も減らされ、責任ある仕事も任されなくなる。
それでも、家計を支えるために、あるいは生活費を得る必要のためだけに、辞めたくても会社に居続けざるを得ない場合も多い。特に、長年にわたり年功序列が習慣だった伝統的日本企業で過ごしてきた人にとっては、上司が自分よりも年下であるだけで面白くない人も多い。
さらに、モチベーションの下がった年配社員の存在は、周辺の若手社員のモチベーションをも下げることになり、「負の相乗効果」が危惧される。各企業の人事担当者には、このような職場の雰囲気の悪化といった心理面でのマイナスを心配している人も多い。
これからの高齢者が能力を発揮しやすい働き方とは
筆者が数多くの高齢者と接してきた経験によれば、彼らは次の働き方を希望する場合が多い。
(1)これまでのキャリアを活かせる
(2)他人に指示されるのでなく、自分が主体的な当事者になれる
(3)現役時代に十分重荷を背負ったため、担う責任は重過ぎず「程々」がよい
一方、「こういった働き方はしたくない」という次の意見もよく聞かれる。
(1)自分より若い人に優位性を示せないような職場では働きたくない
(2)子供に説明できないような職種には就きたくない
(3)フルタイム勤務はしたくない。
仕事はしたいが、結構えり好みをする。だから、こういう年長者側のニーズと、雇用者側のニーズとがなかなか合致しない。お金のために働きたいというよりは社会とつながっていたい気持ちが強い反面、それなりのプライドを持っているので、それが尊重される環境が求められている。
次の二つは、こうした条件を満足した、高齢者が能力を発揮しやすい働き方の例である。
経験師団 - 人生経験を子供の教育に活かす
米国サンフランシスコのNPO「シビック・ベンチャーズ」が始めた「経験師団(Experience Corps)」という活動では、55歳以上の年長者が地元の小学校で放課後に読み聞かせを行う(写真2)。「経験師団」という名称は、人生経験の熟達者が、読み聞かせを通じて子供達に人生の楽しさや厳しさを伝える、という意味が込められている。
しかし、人生の熟達者だからといって子供向けの読み聞かせの十分な技能を持っているとは限らない。そこで「経験師団」では、未体験者に機会を提供し、読み聞かせノウハウを伝達する。これに加えて、各地域での活動母体に対する資金調達や運営も支援する。
米国でも読み聞かせ自体はこれまでも各地域で行われてきたが、大半は個人の善意に依存したもの。一方、「経験師団」では、こうした善意をもつ年長者の経験をより組織的に活用する新しい社会インフラ構築を試みるものだ。7年前にサンフランシスコ郊外の小学校から始まったこの動きは、今では19都市、2,000人の年長者が参加するまでに広がった。
実は、日本でも小学生への読み聞かせは多くの地域でなされている。だが、その担い手は小学校に通う小学生の母親によるボランティアが大半で男性は非常に少ない。
その一方で、読み聞かせは男性でも一度始めると子供の素直な反応に触れられることが新鮮で自分にも刺激になり、のめりこむ人も少なくないという。子供の情操教育に役に立ち、自分も学ぶことができる読み聞かせを通じて、マンネリ化した学校教育に新風を吹き込めるのは、ビジネス経験豊富な男性退職サラリーマンではないだろうか。
ナノコーポ - 雇われないで働く
米国では一人から数人のメンバーでも法人形態をとり、個人事業やボランティアとは一線を画すミニ企業「ナノコーポ」が50代から60代に増えている。ナノコーポとは微細を意味するナノと法人のコーポレーションとの造語だ。
米国国勢調査局は、2002年現在でナノコーポを1,760万人と見積もっている。この数字は、米国の労働人口の約13.5%に相当する。
定年制度のない米国では、60歳より前の年齢で、第二、第三の人生を選択する人が大勢いる。もともと独立自営の人もいるが、近年の傾向は、それまで勤務していた大手企業を退職して独立した元サラリーマンが増えていることだ。
サラリーマンに比べたナノコーポという働き方のメリットは、実際の経験者の意見をまとめると、おおむね次のとおりだ。これらは前掲の「働き方に関するニーズ」を反映したものと言えよう。
- 自分自身がボスであり、自分の仕事の時間を自分で決めることができること
- 退屈な社内会議や社内の官僚的なプロセスに関与する必要がないこと
- 絶対クビにならないこと
- 全てを自分で意思決定できること
- 組織で働くときの給与体系の「不合理さ」がなくなること
- ラッシュアワーでの通勤頻度が減ること
一方、日本ではどうか。総務省統計局の2006年度事業所企業統計から算出すると、労働人口に対するナノコーポの割合は6%。つまり、日本のナノコーポの割合は、まだ米国の半分以下の水準に過ぎない。
しかし、実はこの数値は私が予想していたよりも意外に大きいと感じた。日本ではナノコーポの話をすると「それは面白いアイデアだ。しかし、それは起業が盛んな米国での話だろう?米国は独立起業する人が多いかもしれないけど、日本での割合はそんなに多くないのではないか」という反応が圧倒的に多いからだ。
日本経済新聞の調査によれば、首都圏の団塊世代のうち、65歳を過ぎても働きたいという人が3割を超えている(図表2)。しかし、前述のとおり、居心地の悪い今の会社で65歳まで、あるいは65歳を過ぎても働き続けるより、収入が減っても、組織に縛られずに自分のキャリアを活かして、やりたいことで働き続けたいという人も増えている。
こうした傾向を踏まえると、ナノコーポの形態で働き続ける人が今後日本でも増えていくことが予想される。
FPは「ライフプランつくり」より「ライフワーク探しの応援団」になれ
これまで述べたとおり、これからのサラリーマンは、以前のように必ずしも60歳で定年退職しても離職するわけではない。つまり「定年退職イコール老後の始まり」という区切りがもはや消滅したのである。そして、長寿社会とは、文字通り「生涯現役」の社会となる。
だから、これから必要なのは、定年退職後の「ライフプラン」ではなく、定年退職の有無に関わらず生涯取り組める「ライフワーク」である。したがって、これからのFPに求められるのは、顧客の「ライフワーク探しの応援団」となることで顧客の生涯現役を支えることである。
この意味は、単に老後の生活資金の工面策を説明するだけでなく、たとえば、顧客の後半生に取り組む趣味やテーマ探しを手伝ったり、顧客の能力を活かした地域での活動機会を紹介したりすることである。
長寿社会にはあらゆるものに進化が求められる。FPもその例外ではない。