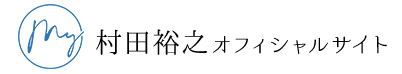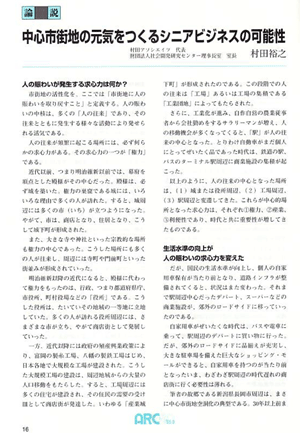2005年9月13日 常陽アーク 2005年9月号論説
人の賑わいが発生する求心力は何か?
市街地の活性化を、ここでは「市街地に人の賑わいを取り戻すこと」と定義する。人の賑わいの中核は、多くの「人の往来」であり、その往来とともに発生する様々な活動により発せられる活気である。
人の往来が頻繁に起こる場所には、必ず何らかの求心力がある。その求心力の一つが「権力」である。
近代以前、つまり明治維新以前では、幕府を頂点とした殿様がその中心だった。殿様は、必ず城を築いた。権力の巣窟である城には、いろいろな理由で多くの人が訪れた。すると、城周辺には多くの市(いち)が立つようになった。やがて、市は、商店となり、住居となり、こうして城下町が形成された。
また、大きな寺や神社といった宗教的な場所も権力の中心であった。こうした場所にも多くの人が往来し、周辺には寺町や門前町といった街並みが形成されていった。
明治維新以降の近代になると、殿様に代わって権力をもったのは、行政、つまり都道府県庁、市役所、町村役場などの「役所」である。こうした役所は、たいていその地域の一等地に立地していた。多くの人が訪れる役所周辺には、さまざまな市が立ち、やがて商店街として発展していった。
一方、近代以降には政府の殖産興業政策により、富岡の製糸工場、八幡の製鉄工場はじめ、日本各地で大規模な工場が建設された。こうした大規模工場の建設は、周辺地域からの大量の人口移動をもたらした。すると、工場周辺には多くの住宅が建設され、その住民の需要の受け皿として商店街が発達した。いわゆる「産業城下町」が形成されたのである。この段階での人の往来は「工場」あるいは工場の集積である「工業団地」によってもたらされた。
さらに、工業化が進み、自作自営の農業従事者から会社勤めをするサラリーマンが増え、人の移動機会が多くなってくると、「駅」が人の往来の中心となった。とりわけ自動車がまだ個人にとってぜいたく品であった時代は、鉄道の駅、バスのターミナル駅周辺に商業施設の集積が起こった。
以上のように、人の往来の中心となった場所は、(1)城または役所周辺、(2)工場周辺、(3)駅周辺と変遷してきた。これらが中心的場所となった求心力は、それぞれ①権力、②産業、③利便性であり、時代と共に重要性が増してきたものである。
生活水準の向上が人の賑わいの求心力を変えた
だが、国民の生活水準が向上し、個人の自家用車保有が当たり前となり、道路インフラが整備されてくると、状況はまた変わった。それまで駅周辺中心だったデパート、スーパーなどの商業施設が、郊外のロードサイドに移っていったのである。
自家用車がぜいたくな時代は、バスや電車に乗って、駅周辺のデパートに買い物に行った。だが、郊外のロードサイドに品揃えが充実し、大きな駐車場を備えた巨大なショッピング・モールができると、自家用車を持つのが当たり前となったいま、わざわざ駅周辺の時代遅れの商店街に行く必要性は薄れる。
筆者の故郷である新潟県長岡市周辺は、まさに中心市街地空洞化の典型である。三〇年以上前までは、長岡市駅前通である大手通は、最も商業施設が集積し、賑わいがあり、それゆえ地価も周辺で最も高いところであった。駅のすぐ隣にあったデパート(長崎屋)で買い物をすることが、見附市や栃尾市といった長岡市周辺の田舎の地域の人たちにとって贅沢なあこがれだった。
だが、現在ではそのデパートは廃業となり、跡地は駐車場として利用されているのみ。駅周辺にあった五軒のデパートのうち、わずかに一軒残っているだけである。かつて地域一番の賑わいを見せた大手通には、シャッターが閉まったままの店舗が目立つ。
代わりに発展が目覚しいのは、国道八号線バイパス沿いに並ぶ巨大なショッピング街である。さまざまなショッピング・モール、低価格品を大量に販売するパワーセンターなどが道路沿いにひしめき合い、さながらアメリカ郊外の街並みのようである。
こうした「駅から郊外への価値の移動」は、都会よりも地方で顕著であり、いまや地方の中規模都市にはどこにでも見られる光景である。
一方、東京などの大都市では、未だに駅周辺の価値が高い。過密な道路事情から自家用車より電車を中心とした公共交通機関の方が、利便性が高いためだ。
人の賑わいの求心力を生み出す「時代の潮流」を読め
さて、こうした流れを眺めると、地方都市において中心市街地が空洞化していくのは都市形成の自然な潮流のように思える。中心市街地と呼んでいるが、実は、空洞化している地域は「かつて中心市街地だったところ」なのである。言い換えると、空洞化している地域には、もはや人の賑わいの中心はなく、別のところに移動しているのである。
このような都市形成の趨勢のなかで、あえて空洞化した地域に人の賑わいを取り戻すにはどうすればよいか。考える糸口は、「時代の潮流」である。
日本は世界の先進国に先駆けて高齢化率が二〇%を超えた。日本の歴史上初の超高齢社会へ移行しつつある。これに伴い、さまざまな情勢の変化が起きている。その変化により、①権力、②産業、③利便性と重点が移り変わってきた人の賑わいの求心力が「次は何に移るのか」の洞察が重要となる。
まもなく定年退職する団塊世代の動向に注目せよ
二〇〇五年というタイミングで注目すべき動きのひとつは、二年後に大量の定年退職を迎える団塊世代を中心とした中高年世代の動向である。
現時点で五〇歳以上の人は、平均的にはお金を持っている。総務省の家計調査によれば、可処分所得では、五〇歳代は全年齢層の中で最も大きい。また、わが国の個人資産一四〇〇兆円の七割は五〇歳以上が保有するといわれている。預金から負債を引いた正味金融資産で見ると五〇歳を超えてから急に大きくなり、六五歳以上が最も大きい。また、人数もいまの若年層に比べると圧倒的に多い。現在の中学一年生は全国で一二〇万人程度だが、団塊世代の最多年代では、倍近い二三〇万人以上いる。
さらに、主婦は、子育てが一段落する五〇代になると、時間的な余裕が出てくる。男性は、退職する六〇歳前後を過ぎると、現役時代に比べて圧倒的に時間に余裕ができる。これらの理由より、企業にとって五〇代以上の人を主要ターゲットとし、経済成熟時代の消費のけん引役と期待する発想は、現時点では妥当だ。
「モノ消費の利便性」から「サービス消費の利便性」へと重点が移っていく
実際、団塊世代周辺をターゲットとしたビジネスがここ数年増えており、いくつか成功事例も出現している。たとえば、もともと近畿日本ツーリストの一部門だった(株)クラブツーリズムは、会員数公称三〇〇万世帯六〇〇万人といわれる中高年をさまざまなクラブ活動への参加を通じて集めている。この活動から発生する旅行需要に対し、企画から交通機関、宿泊施設などの手配を行うことで収入を得る。法人需要の減少で売り上げ低迷に苦しむ旅行業界において、中高年の旅行意欲を取り込んだビジネスモデルを創り、本業である旅行収益の拡大に成功した。
一方、出版社のユーリーグ(株)が手がける「いきいき」という情報誌が五〇代の女性を中心に大人気である。この「いきいき」は、店頭ではなく、定期購読のみの販売だ。創刊時に一七四部だった発行部数が、二〇〇五年八月現在で三八万部を越えている。中高年向けの雑誌は、これまで三〇種類を越えるものが出版され、大半が廃刊に追い込まれたが「いきいき」は、他の追随を許さない例外である。この情報誌を中核に、物販、旅行、カルチャーサービス、共済などへの展開を図り、急成長が続いている。
これらの動きは、中高年世代における人の賑わいの求心力が、従来の駅周辺や郊外のショッピング・モールに代表される「モノ消費の利便性」から、人との出会いを提供する旅行やいきがい探しを支援する情報などの、モノ消費以外の知的・文化的な「サービス消費の利便性」へと重点が移っていくことを示すものである。
アメリカでは、中高年女性専用フィットネスが大ヒット
一方、目を海外に転じると、中高年向けのビジネスで成功している例がいくつかある。九二年にアメリカで設立されたカーブス(Curves)は、既存のフィットネスクラブに不満をもつ中高年女性をターゲットにし、これまでとはまったく異なる新しいサービス形態を考え、大成功した。専門誌アントレプレナーの最速成長フランチャイズの第一位で、店舗数は全世界で九〇〇〇を超え、世界最大のフィットネスクラブ・チェーンとしてギネスブックにも登録された。注目すべきは、顧客の平均年齢は五〇歳。従来型クラブの平均年齢が二五歳なのと対照的に中高年が多い。また、大半の顧客が、これまで従来型のフィットネスクラブに入会したことのない人たちだ。
フィットネスクラブ大国アメリカでも、従来型クラブに背を向ける人は、意外に多い。特に女性には、減量に励む姿を男性に見られたくない、ジムの機械的な雰囲気が好きになれない、長時間拘束されたくない、会員料金が高いなどの理由から、従来型クラブを避ける人は結構いる。
カーブスが、中高年女性にうけているのは、次の五つの理由である。
第一に、女性専用のため、男性の目が気にならないこと。肥満体の女性でも周りに気兼ねなく運動できる。従来型フィットネスクラブには、意外にもそのような場は存在しなかった。
第二に、中高年女性が使いやすい「クイック・フィット」と呼ばれる独自開発の機器を使用していること。従来型フィットネスを避けている女性には、「運動オタク」向きの大規模な機械的な雰囲気を嫌う人が多い。特に、年配の女性にその傾向が強い。
第三に、一回に三〇分ですべての運動を終了できること。従来型フィットネスでは、移動時間を除いても最低二、三時間は必要だ。このため、仕事や家事が忙しいと、クラブに通うのがおっくうになり、退会してしまうケースが多かった。
第四に、従来型フィットネスクラブに比べ、価格が半額以下と安いこと。アメリカの従来型フィットネスクラブの会員料金は、月に一〇〇ドル(約一万二千円)程度で、日本とほぼ同額だ。
第五に、小グループで一緒に楽しく継続できること。実は、これがきわめて重要だ。従来型のフィットネスクラブでは、ジムに行くと、大抵、ペダルのついた機器が窓に向かって一列に並んでいる。横から見ると、まるでブロイラー工場だ。だが、カーブスは、この関係性を一八〇度変えた。体重を落とすための「禁欲的な運動を、同じ悩みを抱えた人同士大勢で楽しくやる」というスタイルを商品化したのが、カーブスの最も卓抜した点だ。
全世界で注目を浴びるカーブスが、ついに日本に上陸した。外食フランチャイズの育成で定評のある一部上場企業(株)ベンチャーリンクが、日本でのマスターフランチャイズ権を獲得し、この春から日本での事業展開を開始、七月四日に東京・戸越公園で第一号店をオープンしたのを皮切りに、年末までに全国一五の地域でマスター店舗をオープンする予定である。
シカゴで大うけの地域密着型シニア向けカフェ
「高齢者意識」をもたない五〇代以上の「新しい高年齢者」向けにサービスを提供し、人気を博しているのが「マザー・カフェ・プラス (Mather Café Plus) 」という新業態のカフェ・レストランだ。現在、シカゴ北部で三店舗展開している。
人気の秘訣は、「年長者向けの場所」というイメージを払拭しながら、年長者の多様なニーズをすくいとる受け皿を多数用意していることだ。
第一に、カフェで提供する食事が比較的低価格でありながら、それなりの質を維持していること。近所の人たちが気軽に何度も立ち寄りやすいように、マザー・ライフ・ウェイズ社が食事の価格を極力低く抑えているためだ。
第二に、店の雰囲気がハイセンスで年寄りくさくないこと。現代的な壁の内装、カラフルな色使い、照明器具の使い方は、お洒落なビストロや大学のカフェテリアをイメージさせる。
第三に、レストランに併設したスペースで四〇種類以上のさまざまなプログラムに参加できる。各クラスの活動を通じて似た興味を持つ人たちとの仲間づくりができることも魅力だ。
第四に、スタッフがきわめてフレンドリーで、温かくもてなしてくれること。若いスタッフが多いが、老年学の知識やディスニーワールドでの勤務経験をもつなど、接客スキルが高い。
このように要求の高い年長者にうけるサービス提供のために、マザー・カフェ・プラスは、さらにさまざまな工夫を凝らしている。その一つが、顧客による提案をメニューに取り入れる制度だ。
具体的には、顧客が参加するアドバイザリー委員会を設置し、サービス・メニューに対する意見をどんどん出してもらう。そして、それらを盛り込んだメニューを次々と生み出し、人気のあるものは伸ばし、ないものは入れ替える。この手順を繰り返し、顧客のニーズ変化を迅速にサービスに反映する。これにより、サービス全体を常に来店者のニーズが反映されたポートフォリオとして維持できる。
また、「マザー・インフォ・プラス」という電話相談サービスも継続的なメニュー開発に役立っている。寄せられる相談が顧客のニーズそのものであり、サービス改善のための有用なヒントを得られるからである。
年長者に人気サービスの裏には、多様な顧客ニーズを迅速に取り入れ、価値あるサービスに転換することのできる、きめ細かなフットワークが存在することを見逃してはいけない。
毎日定期的に行く所のなくなる退職者向けの「第三の場所」をつくれ
社会学者のレイ・オルデンバーグは、かつて自著The Great Good Placeの中で家庭(第一の場所)でもなく、職場(第二の場所)でもない「第三の場所」が、社会的に重要な機能を担っていることを指摘した。 この考え方にヒントを得て、大成功を収めたのがコーヒーショップ・チェーン「スターバックス」であることは有名だ。だが、スターバックスは、現役ビジネスマン以外の人たち、たとえば、家庭の主婦や退職した人たちにとっては、必ずしも居心地のよい場所とはなっていない。
一方、日本の現役ビジネスマンが退職した後に直面する問題の一つは、「行く所がなくなる」ことである。この意味は、外出は頻繁にするものの、毎日定常的・継続的に行く所がなくなるということだ。単に物理的な場所を確保するだけなら、必要な出費をすればよい。だが、問題の本質は、これまで長い時間過してきた第二の場所である職場がもっていた有形・無形の価値に置き換わる新たな「場」が、受け皿として未整備なことだ。
このような視点でマザー・カフェ・プラスを見ると、実は、スターバックスが対象にしていない人たち向けの「第三の場所」としての次の機能を統合的に満たしていることに気がつく。
- 何度も利用しやすいコア・サービスがある
- 新たな友人をつくるきっかけが多い
- 生活に役立つ情報が多く得られる
- 健康維持、教養・スキル向上のための機会が多い
団塊世代の消費行動は、極めて多様であり、「団塊世代」というマス・マーケットは存在しない。このため、商品の売り手が一方的に「生活スタイル」を押し付けるのではなく、多様な機会の選択肢を用意して、顧客に選んでもらうやり方が好まれる。マザー・カフェ・プラスは、まさにこのようなアプローチを実践している例だ。
日本でも団塊世代の最年長者はあと二年で六〇歳、標準的な定年退職の年齢に達する。これらの人たちが、職場を離れてからも、毎日気楽に立ち寄って数時間楽しく過すことができ、人生をステップアップできる場は、今後確実に求められていくだろう。
退職年齢になっても働き続けたいと思う人がふえている
最近、会社を退職したあとも「引退」ではなく、仕事やボランティア活動などを通じて積極的に社会に関わり続けようとする意向が強い(図表1、2)。
一方、別の理由で働き続けたいと思う人もふえている(図表3)。その大きな理由は、年金支給額の引き下げ、支給開始年の段階的引き上げによる年金空白などの経済不安である。人によっては、住宅ローンの支払い、子供の養育費、そして家計のために働き続ける必要があるだろう。このような人は、働き続けたいというよりは、働き続けなくてはいけない人だ。
これと同様の傾向はアメリカでも見られる。かつて、五〇歳前後まで働き、貯まった金で、残りの人生を悠々自適に過す「ハッピー・リタイアメント」が退職後の人生の一つのモデルであった。だが、悠々自適な生活を送りたくても経済的に不可能となり、やむを得ず働き続けなければならない人も多くなった。
現在、アメリカでは六五歳から六九歳の年齢層で仕事をしている人は五人に一人の割合に過ぎない。しかし、AARPの調査によれば、ベビーブーマーの八割は六五歳を過ぎても働きたいと考えている。また、調査会社のローパー・スターチ・ワールドワイドによれば、ベビーブーマーの一七パーセントが退職後に新たに自分のビジネスを始めると答えている。このような就労意識の高まりは、従来のリタイア層には見られない特徴だ。
これからは自分サイズのミニ企業「ナノコーポ」がふえていく
こうした中高年の労働意識の変化が示すのは、今後、定年退職の年齢に近づく人たちには、従来のように「引退」するのではなく、専門性を活かして、自分スタイルで働き続けたい人が確実にふえることだ。
だが、現実は厳しい。五〇歳を過ぎた人が新たに職を得るのが難しいのはアメリカも同じである。したがって、これに対する解決策は、就職先を自分でつくる―つまり、起業することである。
こうして、中高年の起業家がふえているのだが、起業家といっても、売上げを拡大し、会社組織を大きくし、株式公開して一丁上がりという一昔前のネットバブルの時のような志向性を持つ人は、この世代には少ない。会社組織を拡大すれば、いろいろな管理業務がふえ、本来やりたいことができなくなり、本末転倒するからだ。
このため、旧来型の会社ではなく、あくまで自分のやりたいことを、自分サイズの仕事にして、収入を得るスタイルを維持するミニ企業「ナノコーポ(nanocorp)」がふえている。ナノコーポとは、拡大を目指さないという方針を徹底的に追求している超ミニ企業である。従業員は一人から二人で、あくまで自分サイズの事業規模にこだわる。日本でも「一人ビジネス」という言葉があるが、それと似ている。ただし、ナノコーポが、小規模のままでいるのは、競争力を得るための戦略でもある。
「ナノコーポ支援ビジネス」が成長している
ナノコーポのような超ミニ企業は、大企業のような組織的なサポート体制を持たない。したがって、そうしたサポートが、ビジネスチャンスとなる。その一つが、「ビジネス・コンビニ」と呼ばれる業態だ。
一昨年、アメリカの大手宅配会社UPSが、私書箱サービス大手のメールボックス・エトセトラ(MBE)を買収した。私書箱サービスでは、自宅住所を公にしたくない場合、最寄りのMBEを郵便物などの受取り先にできる。このコンセプトが受け、MBEは世界四一カ国、四六〇〇店舗をもつ巨大フランチャイズとなった。当初私書箱サービスからスタートしたMBEも、今ではコピー、印刷、製本、宅配便、文房具など多くのサービスを手がけている。
一方、オフィス・コンビニ大手のキンコーズも、一昨年秋、大手宅配会社フェデックスに買収された。キンコーズも、当初カラー印刷や大量コピー、製本など自宅や会社でやりにくい作業が二四時間三六五日できることが売りだった。だが、その後サービス範囲を広げ、今ではビジネス・コンビニのリーディングカンパニーとなった。
なぜ、ビジネス・コンビニが成長したのか
MBEもキンコーズも主要顧客は、大企業に属さずに独立して働くナノコーポである。ナノコーポの多くは、自宅を主な仕事場にするため、自宅の住所を公にしたくない。また、大会社のような備品のそろったオフィスを持たない。だから、最寄りのビジネス・コンビニが、彼らにとっての「第二のオフィス」となる。これが、この業態が近年成長した理由だ。
アメリカのSOHO(Small Office Home Office)人口は二〇〇一年で四二〇〇万人といわれ、SOHO関連市場は二〇〇億ドル(約二・四兆円)を超えるといわれている。また、二〇〇二年に在宅オフィスがネット接続に費やす金額は一〇二億ドル(約一・二兆円)と見込まれている。ナノコーポは、この膨大なSOHO市場の主役となっているのである。
巨大なSOHO市場を支えるインフラ群
このようにビジネス・コンビニ市場は、ナノコーポを中心としたSOHO人口の増加に伴い成長してきた。だが、この増大の裏には、ビジネス・コンビニ以外のさまざまなハード、ソフト面のインフラの発達があった。
たとえば、エグゼクティブ・スイートと呼ばれる賃貸オフィスがそのひとつである。通常のオフィススペースだけでなく、秘書機能、ミーティングスペース、電話、ファックス、高速インターネット回線、テレカンファレンス機能、オフィス家具、事務用品などを全て取り揃えた賃貸オフィスである。起業する個人に必要なサービスが全てそろっているオールインワンのオフィスで、利用料も敷金、礼金が必要な通常の賃貸オフィスの場合より割安となっている。リージャス社、HQグローバル社など多くの企業がこのようなサービスを全米各地に展開しつつある。
また、SOHO向けの事務用品サービスも重要だ。オフィスデポ、ステープルズ、PCデポなどは、主に個人のビジネスマン向けにパソコン、インターネット、関連用品・サービスを提供することで成長してきた。
さらに、スターバックスやタリーズコーヒーのようなコーヒーショップ・チェーンもナノコーポを支える重要なインフラだ。自宅を仕事場にするナノコーポは、顧客やパートナーとの打ち合わせの場として、これらのコーヒーショップを頻繁に利用する。ちなみにスターバックスは、サンフランシスコ市内でサーカディアという貸しオフィスサービス付きのコーヒーショップを運営している。通常のスターバックスとの違いは、店の中に、専用の会議室があり、ホワイトボードやテレコンファレンス用のテレビや電話が設置されていることだ。また、コーヒーショップの机も通常より広く、書類を広げて大勢で打ち合わせをしやすい配置になっている。
こうした「ナノコーポ支援産業」は、日本でも働く意欲の強い高年齢者の増加に伴い、成長していくことが予想される。
「サービス消費の利便性」に着目した事業モデルをつくれ
これまで述べた成功事例は、単に団塊世代を中心とした層をターゲットにしたから事業が成功したわけではない。継続的な成長のためには、不断の工夫が必要なのは当然であり、勝ち組企業は、それを実行してきたのである。
これらに共通しているのは、社会変化に伴い新たに発生する、モノ以外の知的・文化的な「サービス消費の利便性」に着目した事業モデルであることだ。それは、カーブスでは「禁欲的でなく手軽にやせられること」であり、マザーカフェでは「職場に代わる気軽な行きつけの場」であり、ビジネス・コンビニでは「自宅以外のオフィス機能」なのである。
一方、中心市街地の活性化が叫ばれてから久しい。中央では経済産業省、国土交通省、総務省をはじめ多くの省庁が参加する中心市街地活性化関係府省庁連絡協議会が組織化され、多くの支援策を打ちだしている。だが、いくつかの事例を除くと、その多くが活性化に取り組んでいるというレベルにとどまり、必ずしも成功しているとは言えない。
市街地の活性化のために必要なのは、行政主導による協議会や一過性のイベントではない。日本の歴史上初の超高齢社会への移行に伴うさまざまな情勢の変化を先読みし、その変化が人の賑わいの求心力をどのように変えていくのかを正しく認識したうえで事業に取り組むことである。行政に求められるのは、むしろ、そうした先進的な時代認識をもって事業に取り組もうとする起業家の支援であろう。