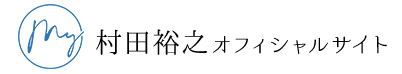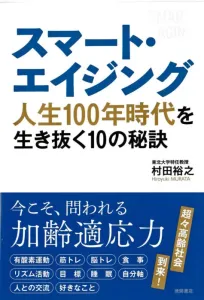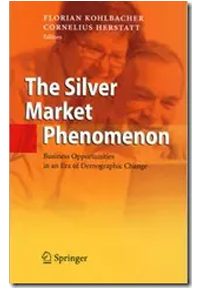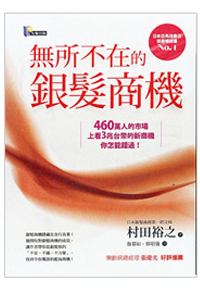私の活動
My activities

スマート・エイジング(Smart-Ageing)とは、「個人は時間の経過とともに、たとえ高齢期になっても人間として成長でき、より賢くなれること、社会はより賢明で持続的な構造に進化すること」を意味します。
これは2006年に東北大学からの依頼で私が提案した概念で、私が所属する東北大学スマート・エイジング学際重点研究センターの組織名にもなっています。
私は、24年間にわたる中高年向け事業と研究を通じて、個人のスマート・エイジングのためには、次の「三つの健康」が必要だと感じています。
一つ目は、自立して生活できるための「身体的健康」。
二つ目は、元気でいきいきと過ごせるための「精神的健康」。
三つ目は、自分らしく生きるための「社会的健康」です。
私の第一の活動は、この「3つの健康」を維持するための勘所を「スマート・エイジングの秘訣」として、主に中高年の個人の方にお伝えすることです。
第二の活動は、個人のスマート・エイジングを支える商品・サービスの開発や利用促進(シニアビジネス)を行う民間企業を支援することです。
そして、第三の活動は、これら二つの活動で得られた知見を、これから社会の高齢化が進む海外諸国に伝えることです。
私たちひとり一人が、高齢になっても元気であり続けることが何よりの社会貢献であり、それは国際貢献にもなるのです。
専門分野毎の活動紹介
Activities by expertise
スマート・エイジング
- 私は、スマート・エイジングを「エイジングによる経年変化に賢く対処し、個人・社会が知的に成熟すること」と定義しました。スマート(Smart)とは「賢い」という意味ですので、スマート・エイジング(Smart-Ageing)」は「賢く齢を加えていく」、つまり「人間として成長していく」という意味になります。世阿弥の言葉を借りれば、散ってしまった「時分の花」を振り返る後ろ向きの生き方ではなく、積極的に「まことの花」を咲かせようとする前向きな人生のあり方がスマート・エイジングです。私たちが「まことの花」を咲かせることは、年齢を重ねるにつれて物事の見方が深まり、視野が広がることで人生が豊かになっていくことを意味します。
シニアビジネス
- 私は日本総合研究所に在籍していた1999年9月に「アクティブシニア市場」の可能性と情報化の進展による「スマートシニア」の出現を予想し、以来24年以上にわたって「シニアビジネス」に取り組んできました。
950以上の企業の事業支援に携わり、女性専用フィットネス「カーブス」の日本への紹介、日本初のカレッジリンク型シニア住宅事業など、時代の一歩先を行く事業に取り組んできました。
また、国内での1500回を超える講演活動を通じて、超々高齢社会の課題を、民間主導の健全な収益事業で解決する「シニアビジネス」を主導してきました。
国際活動
- 2030年までに世界の多くの国が、国連が定義する「高齢化社会(高齢化率が7%を超える)」になります。世界各国が高齢社会問題への関心を年々強め、日本の動向を知りたがっています。私は2004年に世界最大の高齢者NPO AARPがロンドンで開催した国際会議に、唯一の日本人パネリストとして招聘されて以来、スイスでの世界エイジング・世代問題会議にチェアマンとして招聘、シンガポール政府主催SICEX2008の基調講演者に招聘されるなど多くの国際的な活動に取り組んでいます。
著書一覧
Book
 著書
著書
年を重ねるのが楽しくなる![スマート・エイジング]という生き方
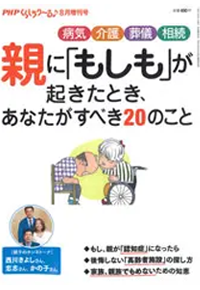 著書
著書
親に「もしも」が起きたとき、あなたがすべき20のこと
 著書
著書
団塊・シニアビジネス 7つの発想転換
 著書
著書
親が70歳を過ぎたら読む本
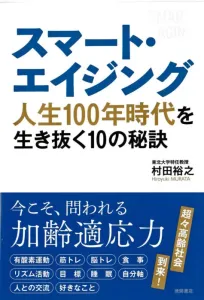 著書
著書
スマート・エイジング 人生100年時代を生き抜く10の秘訣
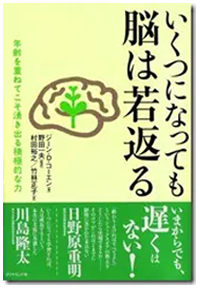 著書
著書
いくつになっても脳は若返る
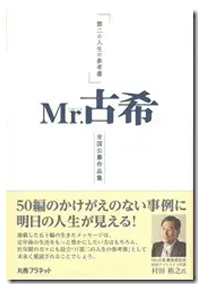 著書
著書
Mr.古希 第二の人生の参考書
 著書
著書
リタイア・モラトリアム
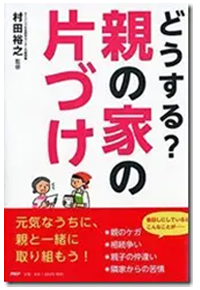 著書
著書
どうする?親の家の片付け
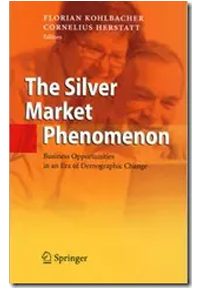 著書
著書
The Silver Market Phenomenon: Bu...
 著書
著書
シニアシフトの衝撃
 著書
著書
成功するシニアビジネスの教科書 「超高齢社会」をビジネスチャン...
 著書
著書
シニアビジネス「多様性市場」で成功する10の鉄則